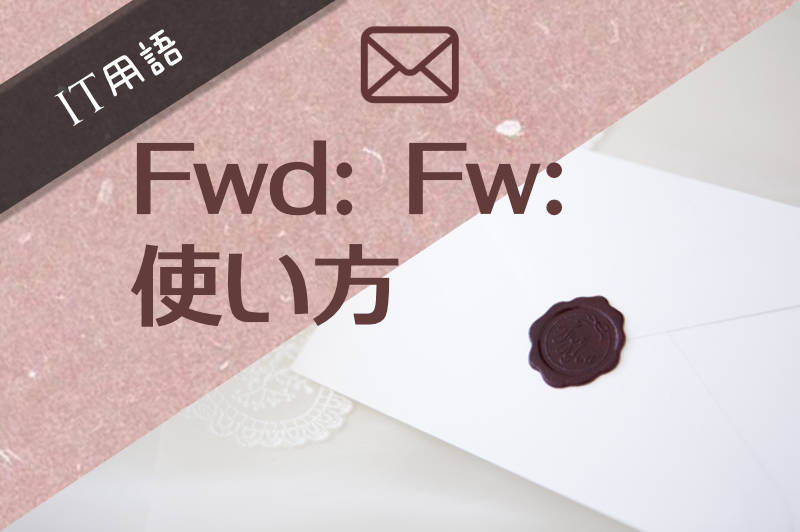こんにちは。
私は個人的に地域のブログを書いているのですが、お店のことを載せるときは必ず許可を取っています。
ところが、無料であっても個人飲食店を営んでいる方には、
「ホームページなんて。」
「ああ、ああいうのうち、やらないから。」
という方もいらっしゃいます。
というのも、多くの方が抱く不安があります。
はじめは無料だけれど、後々いやらしくお金取られるんでしょ。
うちは常連を大切にしているからね。
お客さんがたくさん来すぎても困る。
インターネットなんて信用できない。
地元密着であればあるほど
「いつも来てくれている人を大切にしたい。」という気持ちもありますし、
過度な期待をもって来店し、「期待値に届かなかった場合はネットに悪評価を書かれるのがこわい。」という不安もあります。
記事更新日:2025年2月18日。情報は2025年2月時点。
記事公開日:2020年6月16日。
もくじ
飲食店とITは無関係ではない時代
「飲食店関係」と「IT関係」が全く遠く離れた分野であるというイメージの店主さんも多いのではないでしょうか。
そうでなくても、ただ単に自分がやらないから、よくわからないから、という面もあるかと思います。
「味で勝負。味さえ良ければお客様は来てくれる。」
そんな考え方も少なからずあると思います。
しかしながら飲食店業界にもITの波がすでに迫っています。
ウーバーイーツ
2020年以前から、東南アジアやアメリカなどは、ウーバーイーツなどのサービスが浸透していて、いつでもどこでも好きなものが手に届くのが当たり前の時代になりました。
簡単に言うと、アプリで注文するとサービスに登録している人が買ってきてくれ、家に届けてくれるシステムです。
これが日本でも浸透したのは新型コロナウイルスの環境がきっかけかと思われます。
今までは各店舗に直接注文して出前として届けてもらうシステムはありましたが、
これはアプリ上で一括注文・決済ができて、好きな店舗で好きなメニューを買ってきてもらえるサービスです。
※その国のサービスによってある程度内容は異なります。
これだけの説明だと「今までの出前とどこが違うの?」という感じもしますが、
個人店で物を買う時代と、イオンモールに行って物を買う時代を想像していただければ、なんとなくイメージできるのではないでしょうか。
明らかに違うのは、
「出前」はお店の人が料理を運びます。
ウーバーイーツなどは「ウーバーイーツの人」が料理を運びます。
オンライン(ネット)事前予約
オンライン事前注文をすることで、店側の準備もでき、その分安く提供できるお店も多いです。
テイクアウトは事前ネット注文で何割引き、というサービスを用いているところもあります。
このネット予約はお客さんの数や客層の統計を取りやすいメリットもあります。
ホームページでのイメージ作り
「お店がどういう雰囲気で、どんな客層で、どんな価格帯なのかわからない。」
お客さん側に抱く素朴な疑問です。
「駐車場はあるの?」「子ども連れても大丈夫?」「トイレはきれい?」
など、
来る側の不安を解消してあげることができたらどんなに良いでしょう。
Googleや食べログ、Yelpなどの口コミサイトに書いてもらうのもひとつの手ですが、
お店側で「こんな感じのスタイルだよ」とイメージをつかみやすくしておけば、
お客さんの層も多少コントロールできるメリットがあります。
そのために手っ取り早いツールが「ウェブサイト」いわゆるホームページです。
IT分野への不安
お金がかかりそう。
効果が形で見えない。
そうはいっても日常の仕入れや料理、接客などに追われている状態では、なかなか思うように前に進みません。
「お金がかかりそう」
というイメージは何にでもつきものですが、
「結果が見えにくい。」「形として見えない。」
というものもあります。
ホームページ制作会社にもいくらから作ります。
という安いサービスも多いですが、作ったらたくさん集客効果があるかどうかは別になります。
さらに、維持費もかかるとなればあまり外注で依頼することはおすすめしません。
なぜなら、外注ではその飲食店の人の熱や思いが伝わりにくいからです。
お金をかけないで宣伝する方法
広告について
IT分野はお金がかかりそうだし結果が見えにくい。
だから紙面で広告を発行するという方もいらっしゃいます。
IT分野では、クリックされたらいくらという広告システムも多く、多くが1クリック20~30円から宣伝できます。
1か月の予算を5,000円に設定すれば、それ以上を広告費に搾取されることはありません。(Googleの場合)
「紙面ならもっと安く済ませられるよ」
という人もいるかもしれませんが、インターネット広告はその人の好みなどを分析して、必要な人にだけ広告が表示されるのが一般的です。
しかし私が考えるのが
「無料で宣伝する方法はないのか」
です。
SNSを使う
X TwitterやFacebook、インスタグラム、Youtubeがおすすめ
広告などを用いない限り、ほぼ無料で運用できるのがSNSです。
今では当たり前のようにX Twitterで何かつぶやき、それが市政や国政などに反映するくらいの威力があります。
このXやFacebook、Instagramで営業についてのニュースやメニュー、おすすめの料理などを紹介するのです。
ただ、これには課題があります。
続けることができるか
一番の問題はここです。
日常の業務に加え、効果が見えにくいSNSの運用には少々忍耐が必要です。
業種で異なるSNSの得意不得意
SNSならなんでも良いかといえばそうではありません。
日本のSNSユーザーで最も多いのは2024年時点でX Twitterですが、年齢層が若干高く、テキスト理論の色が強い特色があります。
Instagramは飲食店などに適していますが、ユーザーは若い年齢層の比率が高く、流行り廃りが盛んです。その層がお金を生むかどうかの課題もあります。
先ほど最もユーザーが多いのはXと書きましたが、実際Xよりも年齢の幅が広く、利用している人の数が多いのがYoutubeです。こちらは動画メインとなるため、動画作成に時間をとられるという課題があります。
それではSNSなんてやる意味ないじゃない、と思われるかもしれませんが、
XでもInstagramでもYoutubeでも、認知を目的として、そのお店の人の人柄や思いが伝わればそれだけでも十分な宣伝ではないでしょうか。
無料ブログを書く
アメブロ、ライブドア、はてなブログなど
「アメブロ」や「はてなブログ」「ライブドアブログ」などの無料ブログを開設します。
私が個人的に使いやすい無料ブログは上記の3種類のブログです。
ブログではそのお店の個性が出ます。
言葉遣い、日常生活、ちょっとしたことなど。
仕入の大変さやこだわり、失敗も書きましょう。
X Twitterでは見過ごされてしまいがちなことも、ブログなら一覧で見つけられますので、お客さん側も助かります。
Googleビジネスに登録する
多くが無料
こちらはGoogleマップに自分の店を登録する方法です。これは必須です。
無料でできますし、写真を載せたり、ちょっとしたページも作れます。
なんとなく地図を開いたらうちの店が出てきたよ、という思わぬ効果が生まれます。
宣伝効果を上げる方法
以上のことをはじめてみたけれど、ほとんど見る人がいない。
実はGoogleビジネス以外は、ほとんどがそういう結果になります。
とうのもインターネット上では、ブログやSNSは見てもらうためにそれなりにやり方があります。
ブログの場合
続ける。
内容を充実させる。
ブログの場合、インターネット上において検索で見てもらえるようになるまで時間がかかります。
しかし多くの場合は初月1日の閲覧数が自分だけ、または2~3人というのが3か月も続き、やってられなくなるのが普通です。
ここで大半の人はブログを離脱してしまいます。
逆に言えばライバルが少ない土俵とも言えます。
個人飲食店の人にしかわからない苦労や喜びなどを根気よく書いていくと、ファンがつき、お店の個性が出てくるので、一般の人からの評価もある意味良いフィルターがかかります。
SNSの場合
ターゲット層を絞る。
キーワードを意識する。
一貫性を持たせる。
ターゲット層というのは、「お店が誰に発信したいか」という層を決めるということです。
日本全国老若男女をターゲットにしたいという気持ちはわかりますが、まずはお店に来てもらいたい、またはお店にこんな人たちが多いな、という狭い範囲で絞りましょう。
キーワードというのはハッシュタグ「#」というものもあります。
X Twitterでつぶやいても閲覧数がない。だけど「#三郷」と付けたら三郷市民が見てくれた。
というような感じです。
あとは一貫性。
ブログと違いX TwitterなどのSNSは時系列で流れ、あっというまに情報が去っていきます。
そのため、中華料理店なのに「イタリア料理食べてみた。」とか「釣りしたよ。」とか、一貫性のないつぶやきの連続は固定ファンを獲得しにくいかと思います。
中華料理店が「カップラーメン食べた。」「おすすめ即席中華。ライバル店だけどベタ褒め。」などの方法でつぶやけば、興味がわきます。
まずはファンを増やすために、共感できる一貫したつぶやきや投稿が必要です。
ある程度つぶやき数とファンがつけば、子どものことや家族のこと、いろんな私生活を増やしていくと、人間性も混ざって効果的に認知されていきます。
そんなこんなで考察してみましたが、これも所詮はインターネットの一個人ブログのひとつです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。