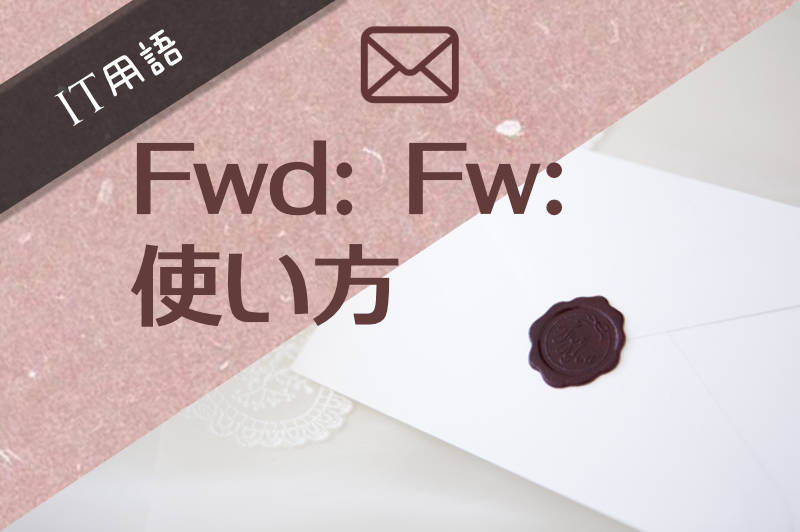こんにちは。
みなさんはインターネットのライブ配信を見たことがありますか?
リアルタイムに配信され、そこにコメントが書かれ、閲覧者との交流が生まれます。
しかし昨今、インターネットライブ配信で問題や事件が起こることも見受けられます。
私の知る限りでは、
ライブ配信で裸体をさらしエスカレートしていく
運転中のライブ配信で事故を起こす
ライブ配信中に危害を加えられる
など
ライブ配信する当事者は複数での運営ではなく、個人で配信することが容易となり、そこから問題に発展するケースもあります。
「ネット発信者はどうしてこんなリテラシーないの?」
そんな声も聞こえてきそうです。
しかし私は発信者だけでなく、そこから起きたとある事故や事件で見られる、閲覧者側の問題も気になりました。
今回は実際に起きた例を用いてネットリテラシーについて考えてみたいと思います。
ライブ配信中に起きた事故・事件の拡散
ケース1
ライブ配信中起きた事故・事件の映像をSNSなどで何も考えず拡散する
配信を見ている人はその現場をリアルタイムにみることができます。
中には配信を録画している人もいます。
アーカイブとして動画の記録が残る場合もあります。
問題はそこから先です。
起こった事故・事件の映像をSNSにアップする人がいます。
中には良かれと思って現場を撮影してSNSなどに情報を拡散する人もいます。
それをさらに拡散する人がいます。
オールドメディアといわれるテレビや新聞などでは映してはいけない映像や写真が、生々しく拡散されていくのです。
何十年もかけて、よりすべての人が不快なく見られるようにコンプライアンスが確立し、そこを監査する団体もいるわけです。
ネット上の真偽不明な情報の拡散
ケース2
インターネット上で生成されたニュースや真偽不明な情報を瞬間的に信じ、拡散する
例えば事実の解釈などを変えたい意思を持つ人が、その世論をひっくり返すために作ったスパム的な情報発信。
中には見分けがつかないほど精巧に生成されたニュース番組もあります。
問題はそこからです。
一方の視点の情報を鵜呑みにして拡散する人がいます。
個人のSNS発信の発言をすべて正しいと思い拡散する人がいます。
タイトルだけを見て中身を判断する人がいます。
インターネットは一度その記事や投稿を見ると、同じような記事や投稿が表示されるアルゴリズムになっています。
なので、一度でも見て信じてしまうと、同じ路線のものが次々と出てくるので、「これは本当の話なんだ!」となってしまうのです。
先ほどオールドメディアの話を出したので、あえて比較すると、テレビや新聞などでは複数の人間が情報の真偽を精査して発信することになっています。
余談ですがアメリカでは100近くチャンネルがあり、うちのメディアはこっち路線で発信するよ、うちはこっち視点で発信するよ、というようにある程度方向性を示しています。
その方が見る側も分かりやすいですよね。
日本のメディアではそのようなことはあまりないので、横一線での発信や報道が多く、それがかえって反発や疑心を招くこともあるのかなと感じます。
これを読んでいる時点でみなさんはインターネットには少し警戒心があるかと思いますが、子どもたちにはそれがわかりません。
インターネット上の仕組みもわかりません。
そんな中、いままでは良くも悪くも守られてきた世界が、一気に個人間で触れることができるようになったのです。
子どもを守ってあげられるのは大人ですが、大人がすでにその渦の中に知らぬ間に入ってしまっているのではないでしょうか。